【日本画】棒絵具とは?棒絵具と藍棒の使い方を解説!【藍色染料も!】
こんにちは、日本画家の深町聡美です。 顔彩と同じ色成分で作られた「棒絵具」 歴史が古く、また使いやすい絵具ですが使用方法を知らない方も多いのではないでしょうか? 今回は日本画の棒絵具の使い方と、棒絵具の前身とも言える「藍...
 日本画|Nihonga
日本画|Nihongaこんにちは、日本画家の深町聡美です。 顔彩と同じ色成分で作られた「棒絵具」 歴史が古く、また使いやすい絵具ですが使用方法を知らない方も多いのではないでしょうか? 今回は日本画の棒絵具の使い方と、棒絵具の前身とも言える「藍...
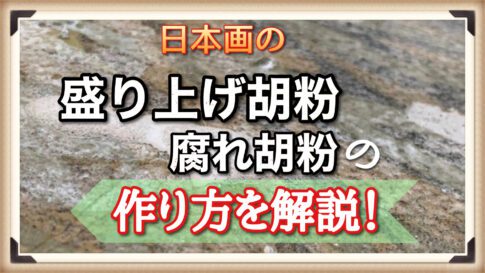 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga日本画の表面を盛り上げたい人 こんな人におすすめ!新しい質感表現を模索している絵描きさん 新しいことを学ぶのが好きな絵描きさん 皆さんは美術館で、絵の表面が盛り上がっている 日本画を見た事がないでしょうか? 日本画でも油絵やアクリル画のように、 ボコボコとした質感を出すことができるのです。 盛り上げ用のペーストなど、やり方は様々ですが 最も基本と言えるのが「盛り上げ胡粉」です。 今回は、明治時代の日本画の技法書 「丹青指南」に描かれた、 盛り上げ胡粉の作り方を 現代語訳して分かりやすく解説いたします!
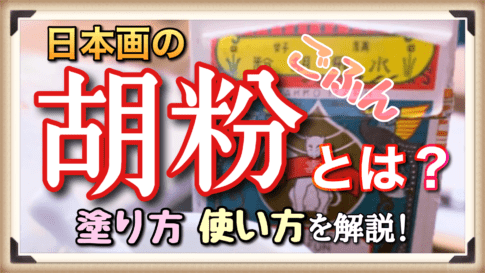 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga・胡粉を溶かして使えるようになる!・胡粉の種類が分かって使い分けられる! こんにちは、日本画家の深町聡美です。 「日本画といったら胡粉!」と美術の授業や日本画体験会でも使われることが多い胡粉。 日本画の体験会などに行った...
 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga・失敗しない最強の膠水が作れる!・膠の濃度や溶かし方の疑問が解ける! こんにちは、日本画家の深町聡美です。 日本画を描く上での超必須アイテム。それが、膠です。 これがなければ、日本画ではないと言っても過言ではないかも知れ...
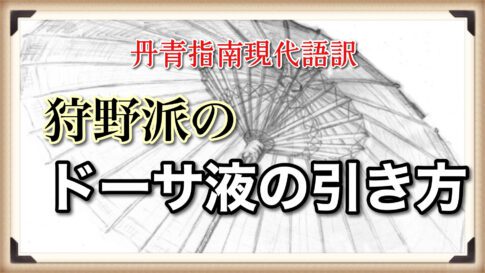 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga才能あふれる狩野派の画家たちも、努力なしに何でも描けたという訳ではありません。もちろん想像のつかないような努力、そして練習をしていたに違いありません。そこで何百年も伝統を受け継ぎ続けた狩野派の絵師たちは、一体どんな練習をしてきたのでしょうか!?今回は狩野派で代々使われてきた練習用スケッチブックの作り方と、前回の記事で作ったドーサを紙に塗る(引く)方法をご紹介いたします!
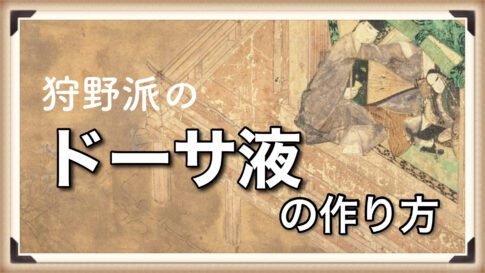 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga絵を描いているうちに、岩絵具が剥落したり、水を吸い込んで発色が悪くなったり、直しているうちに、時間がかかって間に合わない!直しても直しても、色が元に戻らない!!それはドーサ(にじみ止め)の作り方が悪いからかも知れませんよ。 今回はそんな悩みを解決する、正しいドーサの作り方を、狩野派伝統の日本画技法書「丹青指南」を引用しながら解説いたします
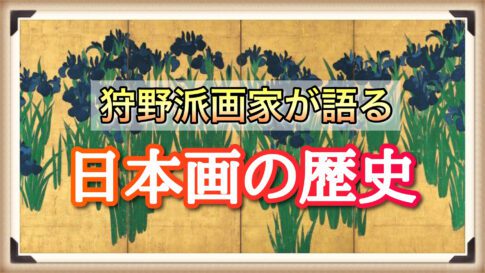 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga今回は日本画の技術書「丹青指南」から、日本画の歴史を紐解いてみましょう!日本画と言えば雪舟!と思っていたけど、美術館で見る絵は何か違う……と思ったことはありませんか?この記事では中国の絵や雪舟との意外な共通点が見えてきます。日本史の狩野派に負けてしまった方も、シンプルにまとまっていますので日本の教養として、いっしょに復習してみませんか?
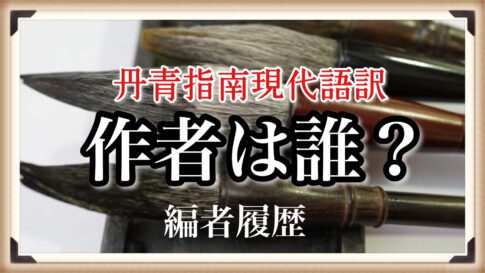 日本画|Nihonga
日本画|Nihongaこんにちは、日本画家の深町聡美です。 第3回目の今回は、編者履歴部分の現代語訳です。 前回、前々回の繰り返しが多いので、今回はサクッと本題だけ掲載しますね。 これまでの記事はこちらから! ➡日本画の精神を、...