【伝統色】黄土色の意味・原料・日本画での使い方をわかりやすく解説
黄土色とは?どこの土?実は1色じゃない!日本画で使われる伝統絵具・黄土色の秘密や作り方を図解付きで丁寧に解説します。
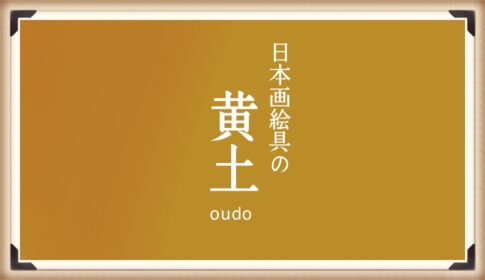 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga黄土色とは?どこの土?実は1色じゃない!日本画で使われる伝統絵具・黄土色の秘密や作り方を図解付きで丁寧に解説します。
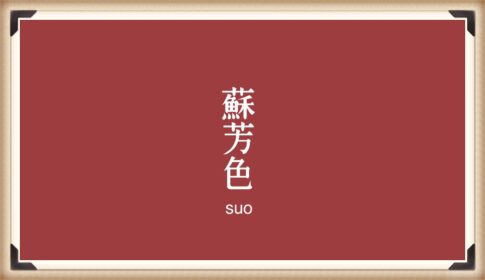 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga今回は 蘇芳色(すおういろ) をテーマに、蘇芳色は高貴な色、由来は木の色素、漢字の意味、蘇芳絵具の作り方を解説していきます!
 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga日本画絵具「朱土(しゅど)」とは?黄土を焼いて作られる安全な赤い絵具、朱土の特徴や使い方を徹底解説!水銀朱との違い、大和絵での活用例も紹介。水干絵具の基本も分かります!
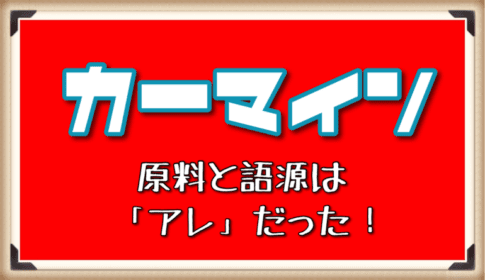 日本画|Nihonga
日本画|Nihongaカーマイン(洋紅)とは?虫由来の鮮やかな赤い絵具の意味・語源・歴史を徹底解説。日本画に伝わった背景や、現在使われているカーマイン絵具についても詳しく紹介します!
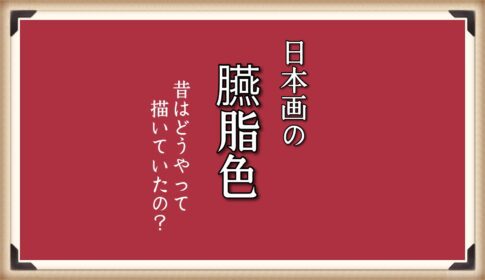 日本画|Nihonga
日本画|Nihongaえんじ色とは?日本画に使われた伝統的な絵具の由来と、江戸時代の狩野派による使い方を詳しく解説!丹青指南に基づき、昔の日本画技法や材料について学べます。
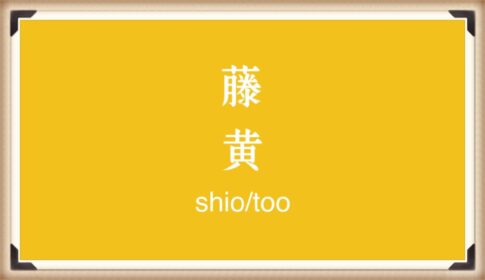 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga日本の伝統色「藤黄」は「しおう」「とうおう」と読む黄色い絵具。その名前の由来は猛毒鉱物と樹脂にあった!色の秘密や使い方を解説!
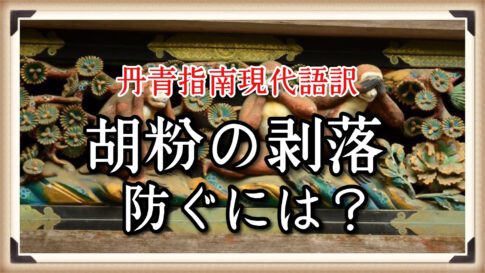 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga絵具や胡粉が剥落する原因は、実は“塗り方”ではなく“溶き方”にある——狩野派の絵画技法書『丹青指南』をもとに、日本画の保存技術を読み解きます。
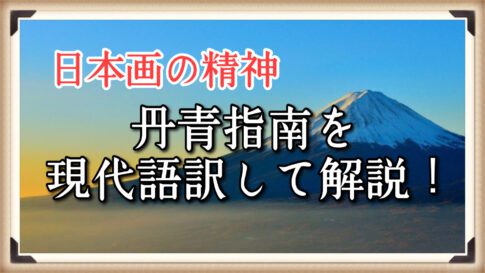 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga狩野派の彩色職人・市川守静。「今の日本画は彩色の基礎が失われている」——その危機感から、幻の技法書『丹青指南』は生まれた。この記事では、その現代語訳と、背景にあるドラマを深掘りします。
 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga日本画の混色絵具、草汁、ウルミ、合わせ黄土、丹墨、艶墨、朱肉色、白緑茶、黄土茶、丹墨茶の作り方を図解入で解説します。
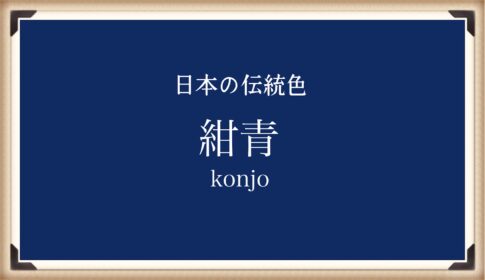 日本画|Nihonga
日本画|Nihonga日本の伝統色「紺青」は群青と同じ成分ながら、より濃い色をしているのが特徴です。ここでは名前の由来や群青との違いを解説します。