こんにちは、日本画家の深町聡美です。
鮮烈な赤でカッコいいカーマイン色!
小学校の色鉛筆になんとなく入っていて、
なんとなく知ってる「カッコいい色」
と思っていませんか?
実はこの色、知ってビックリな
- 材料はカイガラムシ!
- 語源もカイガラムシ!
- でも日本では「洋紅」と呼ばれた高級絵具!
なんです!
今回は
- カーマイン(洋紅)と虫の関係
- カーマイン(洋紅)の絵具の作り方
- カーマインが日本で親しまれた歴史
の三点を解説していきます!

Contents
カーマインと洋紅の違いとは?色味や特徴をわかりやすく紹介
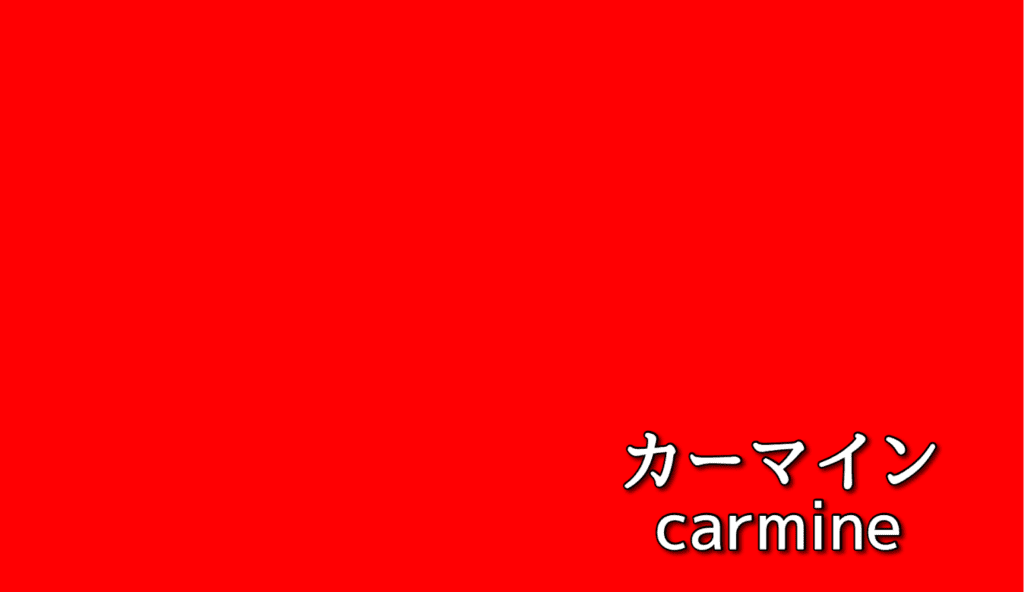
| 英語 | carmine |
| 和名読み方 | ようこう |
| 16進数 | #BE0039 |
| RGB | (190,0,57) |
| マンセル値 | 2.5R 4.0/14.0 |

元々同じ原料からできた近い色です!
カーマインは鮮やかなピンク寄りの赤で、
洋紅は暗い赤…
そんなイメージがあるかもしれません。
実際、洋紅とカーマインは違う色のように
書かれることも多いですが、
カーマインと洋紅は同じ原料でできた色なんです!
カーマイン(洋紅)の原料はカイガラムシ!?虫由来の赤色の秘密


カーマインも洋紅も、原料はカイガラムシです。

げっ!気持ち悪い!

でも昔は飲食物にも使われていたそうです。
カーマインと洋紅の原料はカイガラムシ!
中年米に育つウチワサボテンに寄生している
コチニールカイガラムシのうち、
産卵前の雌のみが材料になります。
このカイガラムシをサボテンから採集し、
すりつぶすと赤い粉末になるんです。
これをコチニールと言います。
水に溶かしてライム果汁に入れると
ライムの酸と化学反応を起こしオレンジ色になります。
オレンジ色のライムジュース…
原料を知らなければ普通に飲めそうですよね。
なので、昔はコチニールを
食べ物にも使っていました!
皆さんが知っている有名ジュースも
コチニールが入っていたかもしれません…
気になる方は調べてみて下さい!

現在はコチニールアレルギーなども知られ、規制の方向にあるようです。

ある意味、昆虫食の走りだったのかも…?
↑カイガラムシの染料です
カーマイン(洋紅)ってどんな意味?語源はカイガラムシだった!
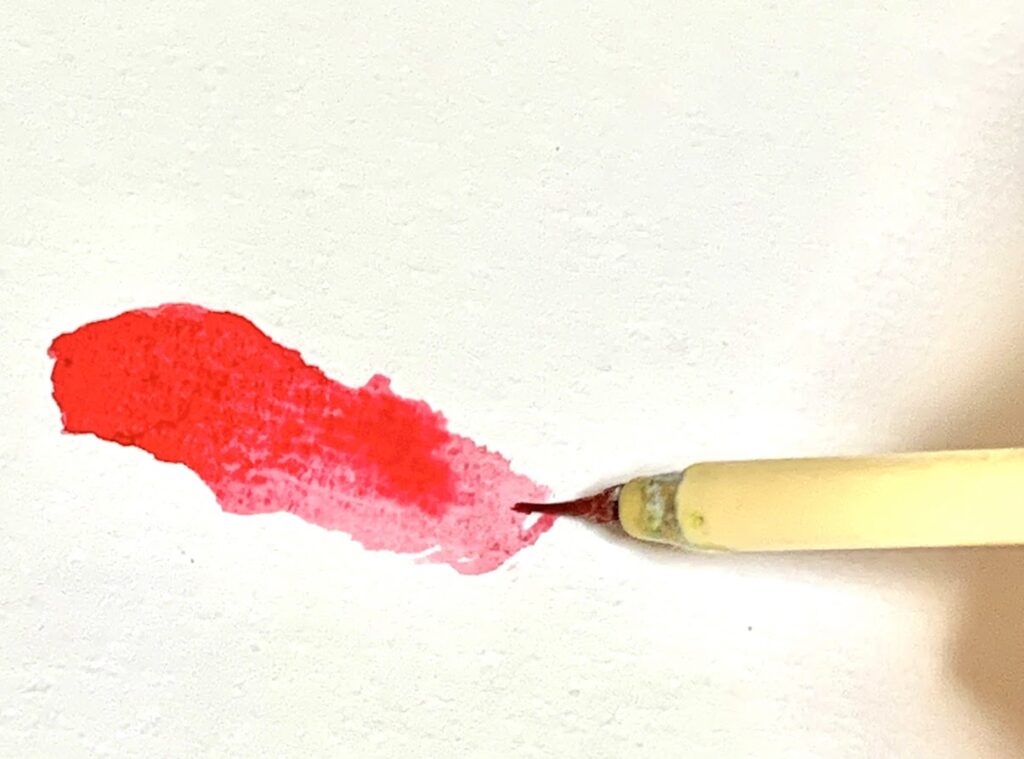

それにしてもカーマインってかっこいい名前だよね!
どんな意味なの?

それもカイガラムシという意味です!

また虫なの!?
カーマインは
「ケルメスカイガラムシから採取された染料」
というラテン語に由来しています。
さらに遡ると、サンスクリット語で
「虫が作った」を意味する言葉が元になっています。
クリムゾンもカーマインと同じ語源です。
当時は恐らく、身近な虫で簡単に作れる
鮮やかな色材として重宝されたはずです。
数々の地域と文化を超えて
大事にされた技術と生物だったのでしょう。
一方「洋紅」は、そのまま「西洋の紅色」。
後述するように南蛮貿易で渡来したことによります。
ケルメスカイガラムシ?
ケルメスカイガラムシはメキシコのコチニールカイガラムシと同様に、赤い染料が採れる虫です。このように赤の原料となるカイガラムシを「臙脂虫」と呼びます。
カーマイン(洋紅)の絵具とは?原料と特徴、使い心地を解説
現在のカーマインは植物由来ーコチニールとの違いとは?


じゃあカーマインと洋紅の材料って虫!?

今は植物の色素で出ていているから安心して!
コチニールを使った絵具には、陽光の他に
- カーマインレーキ
(クリムソンレーキ)
があります。
ですが、前述したような
コチニールアレルギーという健康被害もあり、
現在のカーマインにはカイガラムシは使われていません。
茜という植物から採れるアリザリン色素、
アロエなどのアントラキノン色素
植物が持つ色素を元に、化学的に作られています。

現在、カイガラムシを使った絵具は、コチニールという名称で販売されています。
カーマインレーキの意味と特徴ー染料を使いやすくするレーキ顔料とは

そういえばカーマインレーキの「レーキ」って何?

染料を、水に溶けないようにすることです!
さて、コチニールを使った絵具は洋紅の他に
カーマインレーキ(クリムソンレーキ)がありました。
※前述したように現在は植物から作られています。
ですがコチニールは染料なのでそのままでは
絵具として非常に使いにくいんですよね。
藍や蘇芳も染料なので
同じ問題がありました。

コーヒー染めで頑張って絵を描く感じかな…
そこで、化学の力で不溶性に変えてしまいます。
こうして不溶性になった染料の絵具を
レーキ顔料と言います。
赤い染料をレーキにしたので
- カーマインレーキ
- クリムソンレーキ
というわけです。
カーマイン(洋紅)の絵具はどんな感じ?使い心地と注意点まとめ


コチニールのカーマインは、鮮やかだけど色褪せやすいから気をつけて!
コチニールのカーマインは
透明感があり、鮮やかとされています。
しかし他の染料系と同じく
日光に弱く、すぐに褪色してしまいます。
また、黒変するという話もあります。
日本画においては江戸時代から
朱よりも透明感がある赤色として使われていました。
ただし、日本画の赤系染料の絵具は
重ね塗りをしても表面まで染め上がってきて
なんとなくピンク風になる可能性があります。

重ねても重ねても永遠にピンクが残る…
そんな記憶があります。
カーマイン(洋紅)はどうやって日本に伝わった?狩野派と江戸時代の赤い絵具


この章では
「コチニール=カーマイン=洋紅」
とさせていただきます!

現在コチニールとされる赤い粉は、
上陸当時は「洋紅」と呼ばれ、
その原名として「カーマイン」がありました。
コチニールが日本に上陸したのは
江戸時代!
1844年から1848年とされています。
蘇芳が飛鳥〜奈良時代に伝来したので、
それと比べると意外と最近な感じがしますね。
長崎に貿易にきたオランダ人によって
赤い粉末として大量に流入しました。
それが狩野派の絵師に送られ、
狩野探淵守真がカーマイン(洋紅)として使い始めます。
狩野派では臙脂に混ぜて、
紅色の花類(衣類説あり)だけに使われました。
また、藍色に混ぜて紫色としても使っています。
コチニールの価格と品質の歴史ー日本画で重宝された高級絵具とは

昔は食べ物にも使われた染料というと、
とても安価な気がしますよね…
ですがコチニールは昔は非常に高価でした!

現在も価格が高騰していて、決して安い絵具ではありません。
1g約1000円くらいです。
※参考:絵具屋三吉
江戸時代に日本上陸した後
コチニールはすぐに国内販売されました。
大正時代の日本画技法書には
杉山仙助という絵具商が販売していたという
記録が残っています。
そのときのコチニールを使った洋紅は
品質が大変よく、水を注ぐだけですぐに溶け
余計な物が沈んでいることもありませんでした。

不純物が入っていなかったんだ!
しかし、その後は徐々に
品質が落ちていってしまったそうです。
ですが、コチニールの質が落ちてしまっても
今は新原料のカーマイン、洋紅の絵具があります!
次章では日本画の洋紅を見ていきましょう!
日本画で使われるカーマイン(洋紅)ー水干絵具や顔彩で楽しもう!


日本画では水干絵具や顔彩で見かけるね!
日本画の洋紅は水干絵具や顔彩で見られます。
洋紅と書いてあったら、
「カーマインのような鮮やかな赤色」
と覚えておくと良いでしょう。

水彩絵具のように使える
チューブ絵具もあります!
まとめーカーマイン(洋紅)とは?意味・由来・虫との関係を徹底解説【日本画にも使われた赤色】
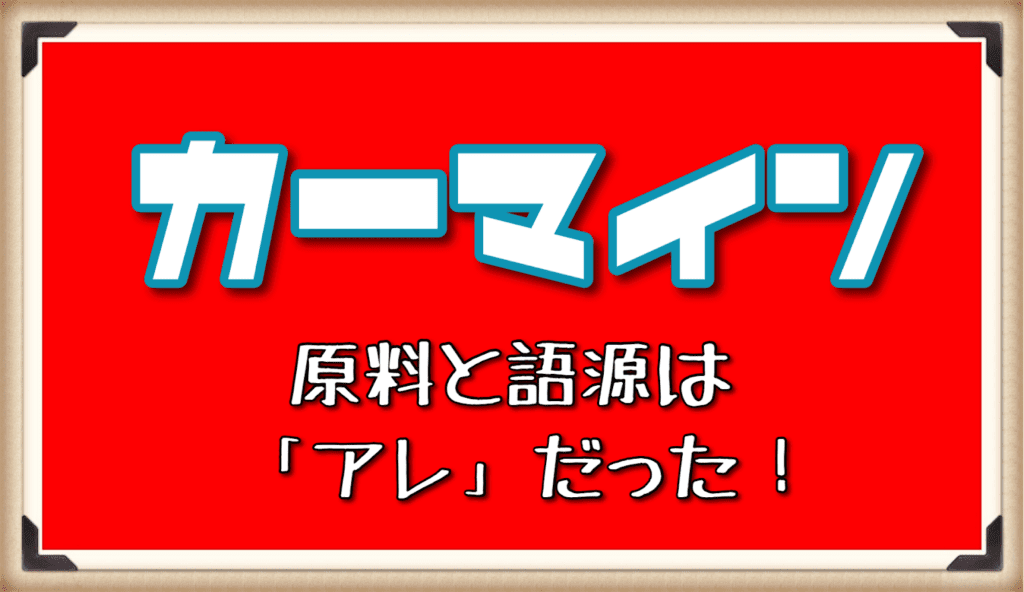
以上、カーマイン(洋紅)絵具についてまとめました!
- カーマインの日本名が洋紅!
- カーマインは鮮やかな赤!
- カーマインの原料は虫だった!
- でも昔は鮮やかで透明度が高い高価な絵の具だった!
コチニールが虫から採れる赤なのは有名ですが
それから作った絵具が高価だったことは
意外と知られていないと思います。
今回の記事で絵具に詳しくなった皆さんは、
ぜひ純正のコチニールをゲットして
染めたり塗ったりしてみましょう!
本物のコチニールは
〇絵具屋三吉
〇得應軒
などで購入できます!

アレルギー体質の人は気をつけて使いましょう。
『丹青指南』は、江戸時代の絵師たちが使っていた技法書です。
色の名前や使い方が細かく書かれた、
貴重な日本画の資料を
現代語訳+注釈つきでまとめました。
👇本格的に学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください👇
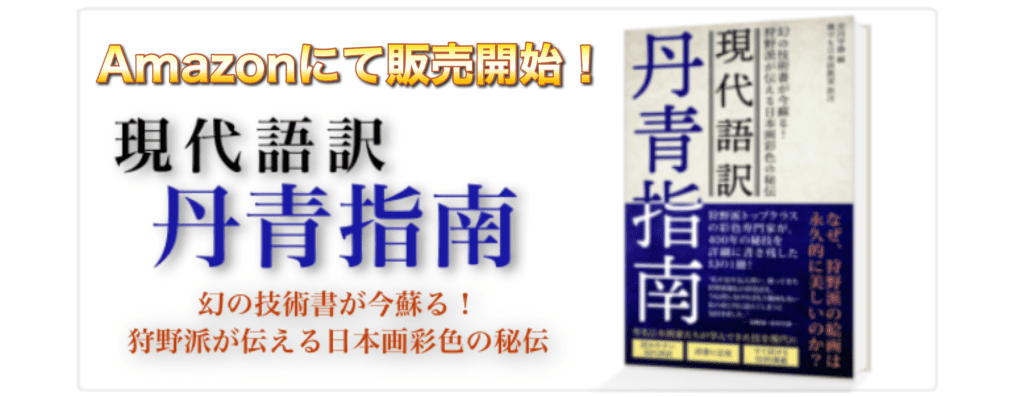
カーマイン(洋紅)絵具まとめ
本物のコチニール!
天然染料をナチュラルなまま
販売しているメーカーです。
商品画像は一見の価値アリ!
実験やお子様との遊びにも使えそうです。
買うならセットがおススメ!
顔彩の洋紅は
12色セットにも入っています!
同梱の臙脂や朱色と比べるのも
おもしろいですよ!
チューブなら日本画も簡単!
日本画絵具はむずかしい!?
でもチューブ絵具なら
絵皿に出すだけで簡単に
日本画絵具が使えます!
水彩感覚で描きたい方にオススメ!

参考(一部)
・ケルメス|wikipedia
・コチニール色素|wikipedia
・色の名前はどこからきたか
・日本画画材と技法の秘伝集
・日本画用語事典
・丹青指南
・日本色彩事典|武井邦彦
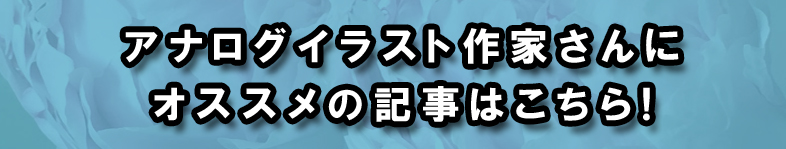

前の記事はこちら!
⇒【能舞台も】朱土とはどんな絵具?日本画絵具の使い方を解説!
次の記事はこちら!
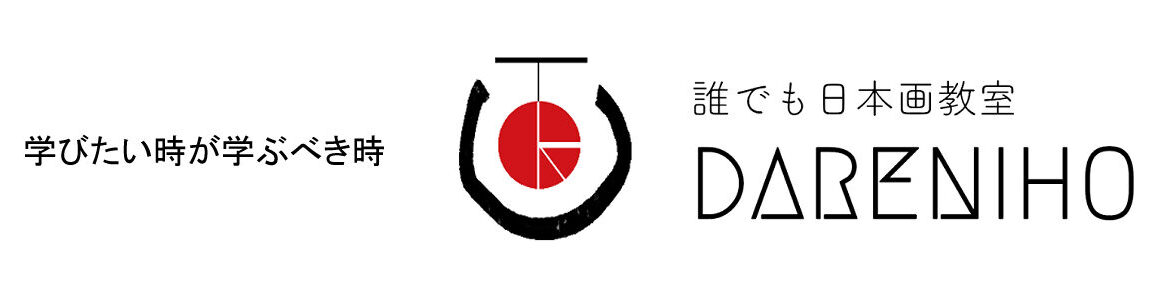


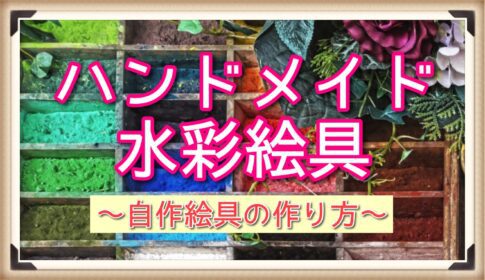

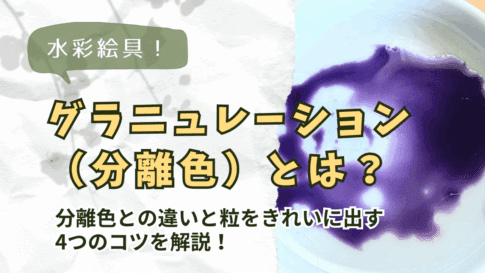

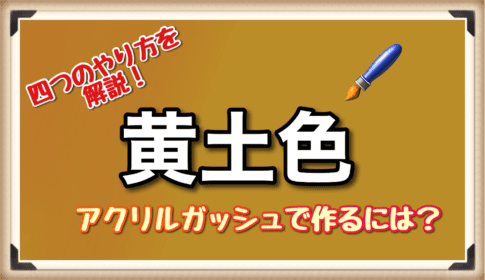

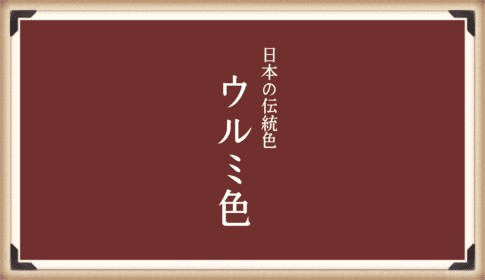
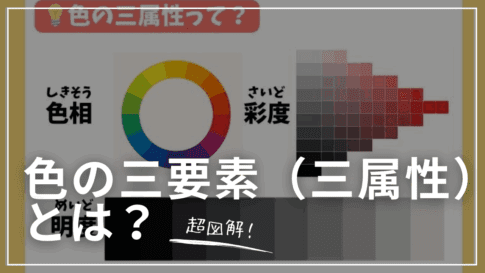
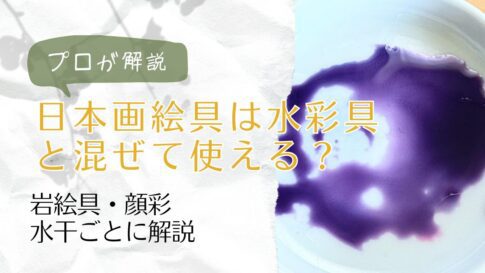

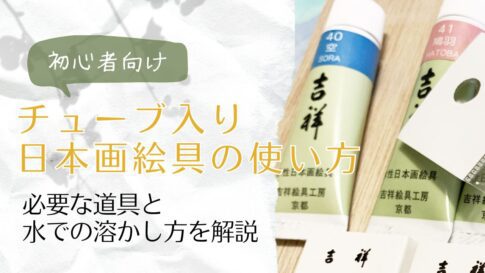
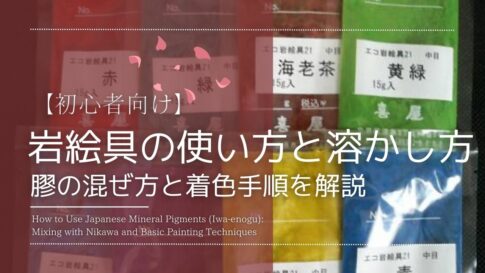

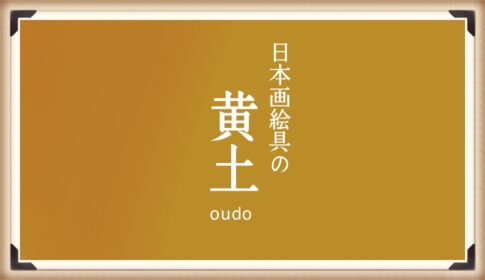
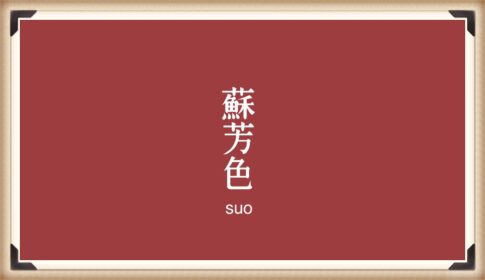

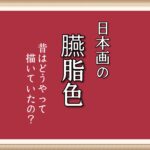
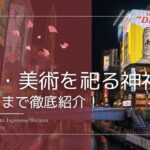


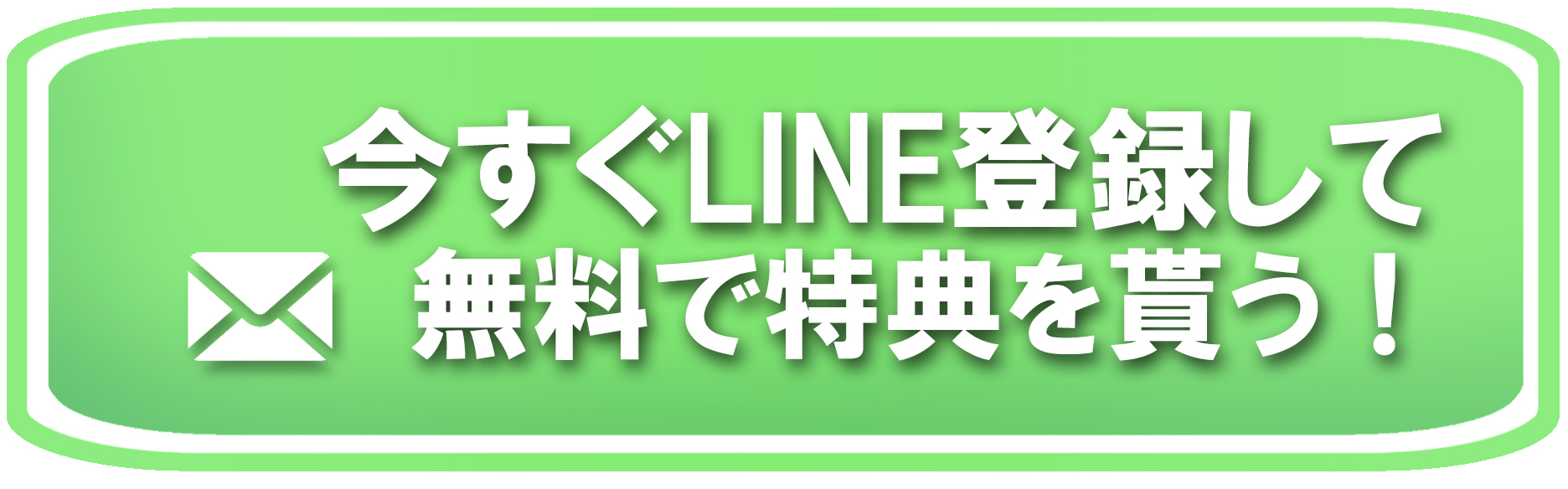

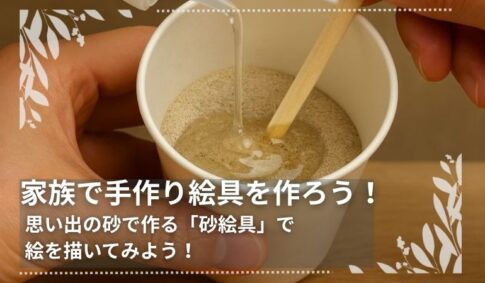

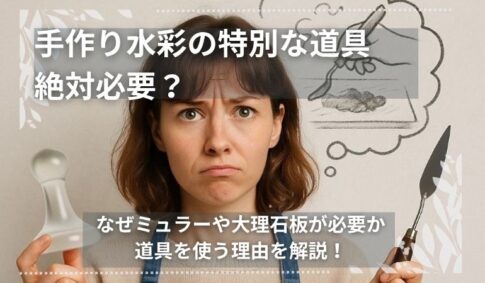

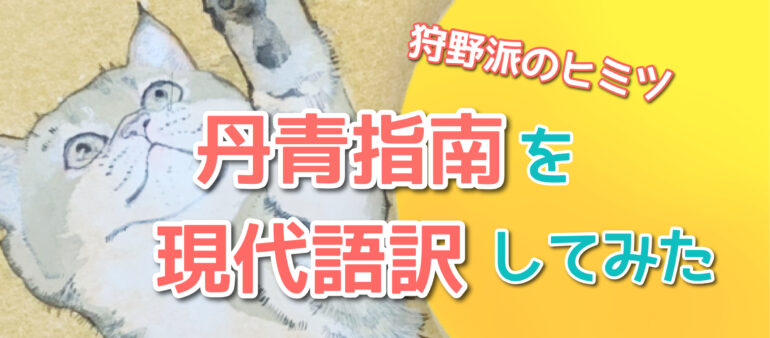

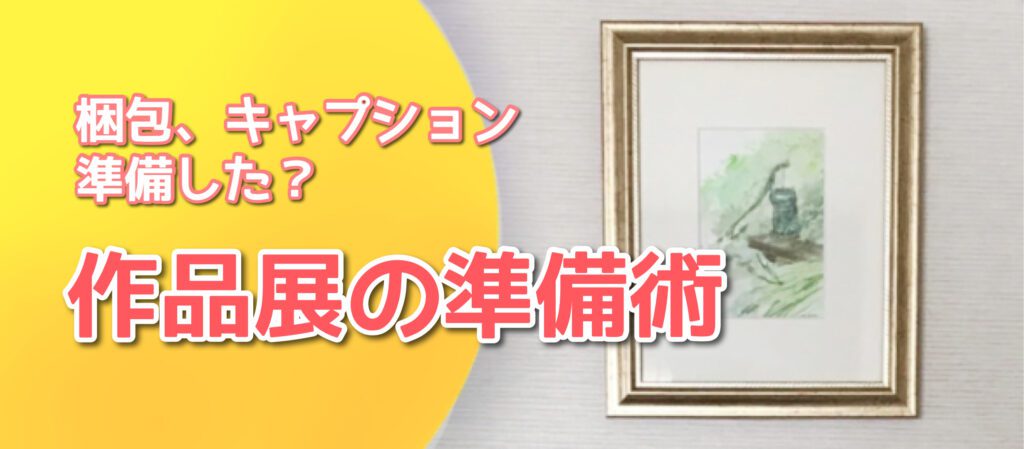
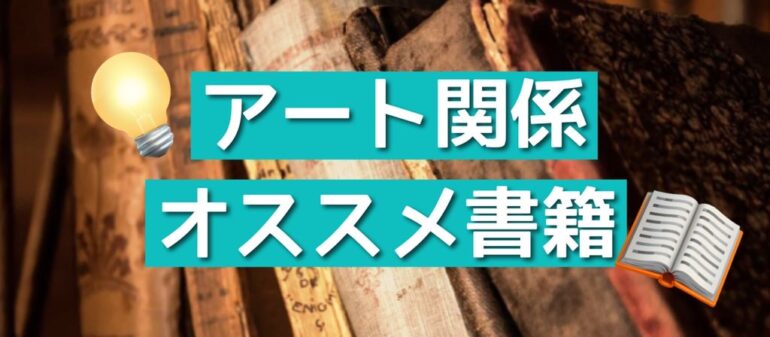
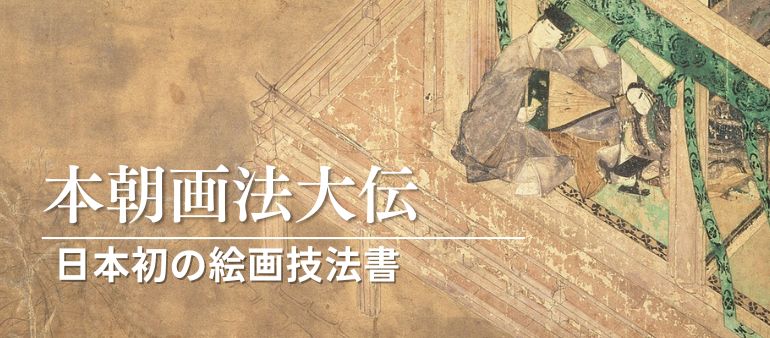

カーマインと洋紅って同じ色なの?