日本画において、筆はただの道具ではありません!
一本の筆の中には、繊細な線を描くための仕組みが詰まっています。
ここでは、日本画筆の筆の各部の名称とその役割について解説します!

Contents
日本画で使われる筆の部位と名称
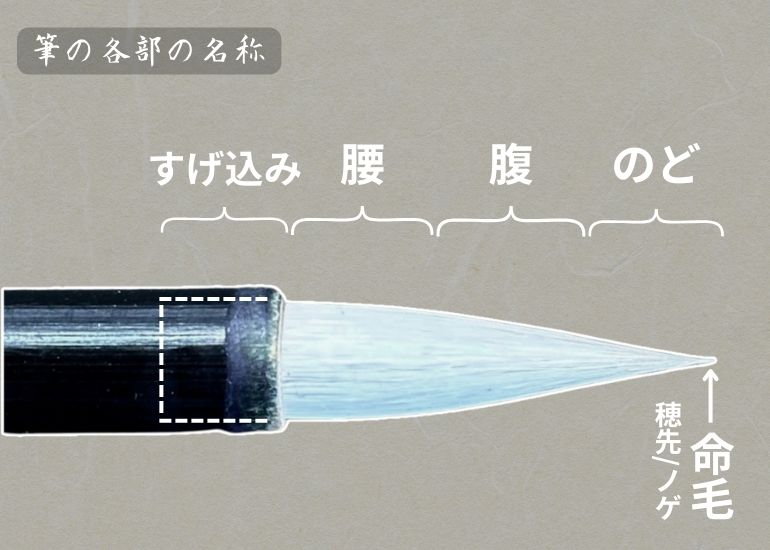

名前を覚えておこう!
日本画筆は、根元から
- すげ込み
- 腰
- 腹
- のど
- 命毛(穂先/ノゲ)
で構成されています。

「コシが強い」っていうのが筆の腰のことなんだね!
筆の「すげ込み」とは?日本画筆の構造を支える接合部

筆軸と穂の根元を固定する部分です。
「穂を軸にすげ込む」ことからこの名が付きました!
毛をしっかりと固定し、穂が抜けないように整える重要な接合部です。
筆の「腰(こし)」の役割とは?線に強弱を生む構造ポイント

穂の根元に近く、筆の「力の入り口」です。
コシのある筆はこの部分がしっかりしており、
線に張りや弾力を生みます。
筆の圧力に応じて反応し、
筆圧に強弱をつける際の要となるんです!
筆の「腹(はら)」で決まる!絵具の含みと安定した線

穂の中腹で、絵具や水分を多く含む部分です!
含みの良し悪しはこの「腹」によって決まります。
長い腹を持つ筆は、
長く一定の線を引き続けることができます。
のどとは?日本画筆の構造で自然な線を生む絞りの部分
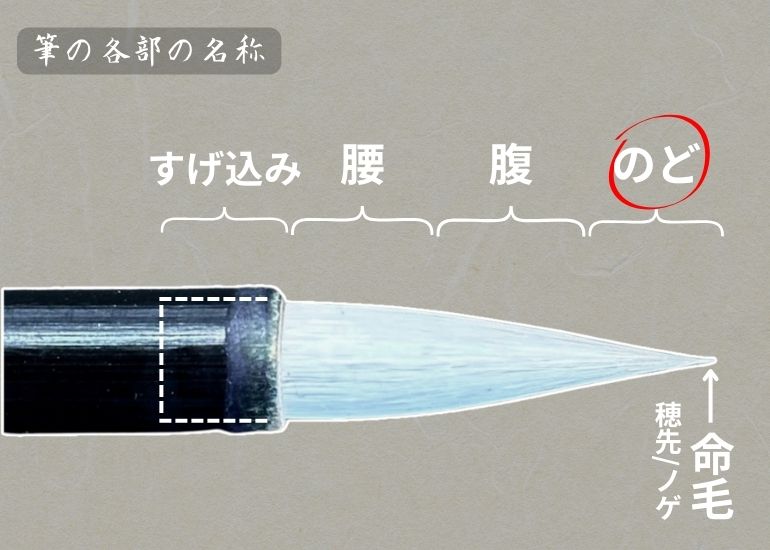
穂先に向かって細くなる部分。
「のど」の部分がスムーズに絞られているほど、
線に自然なグラデーションや強弱が生まれます!
命毛(いのちげ)|筆の穂先で線のキレを決める繊細構造
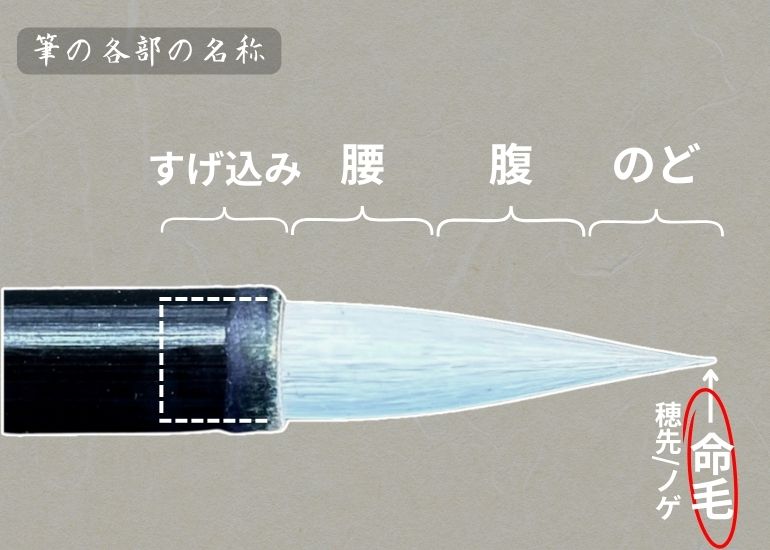
命毛とは、最先端の毛。
まさに筆の命ともいえる繊細な部分です。
命毛が効いている筆は、
最後の「抜き」の瞬間まで美しく線が決まります!
これが絵の締まりになるのです。
そして、穂先のまとまりと鋭さを左右する重要部位でもあります。
まとめー日本画筆の構造とは?各部の名前と役割をやさしく解説!

最後までお読み頂きありがとうございます!
日本画筆は、
- すげ込み
- 腰
- 腹
- のど
- 命毛
といった複数の部位で成り立っていましたね!
それぞれの構造は
✅筆圧の変化
✅線の強弱
✅絵具の含み
✅線のキレ
などに影響を与えています。
これをコントロールするのが、職人技!
筆は単なる“毛の束”ではなく、
職人技が込められた精密な道具なのです!
筆の構造を理解することで、
筆のことがもっと好きになって頂ければ嬉しいです!
ぜひ、自分の筆をじっくり観察しながら、
今回ご紹介した部位を意識してみてくださいね。

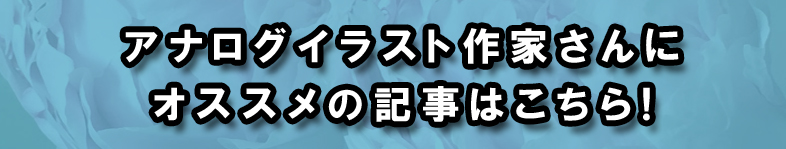

前の記事はこちら!
次の記事はこちら!
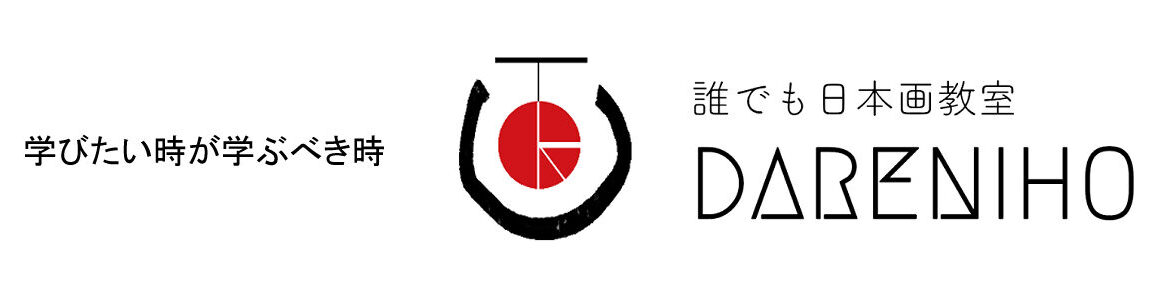


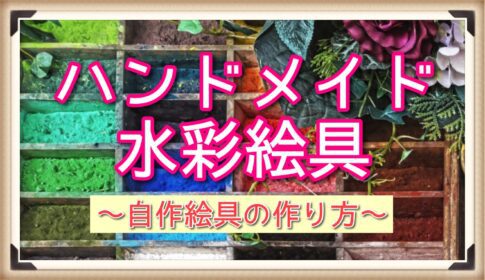

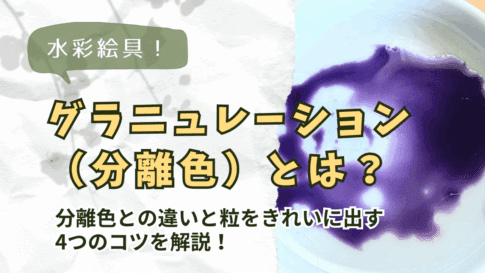

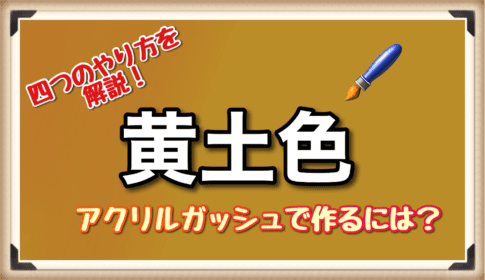

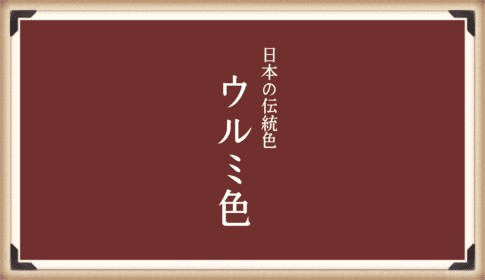
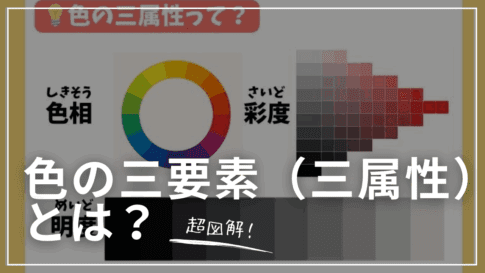
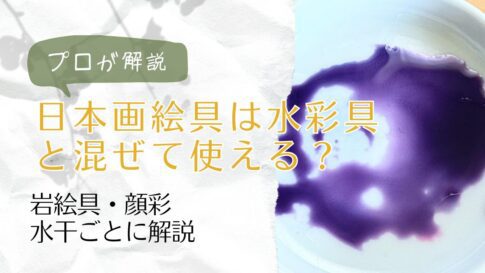

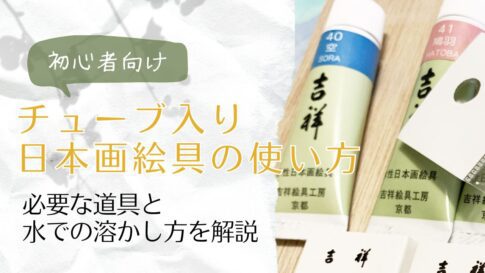
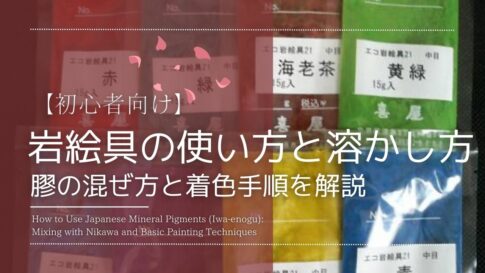

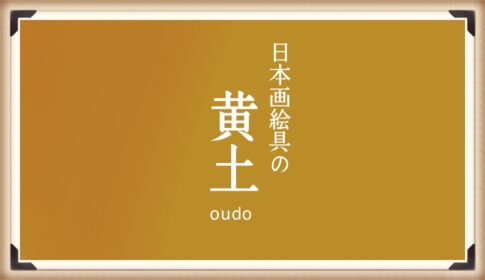
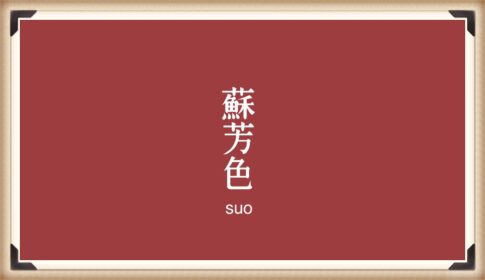
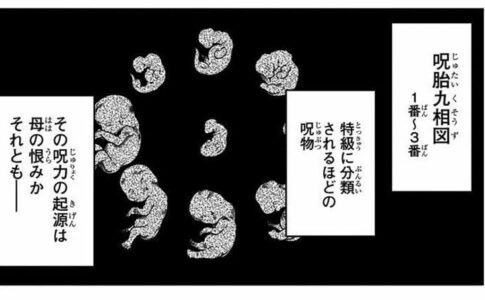
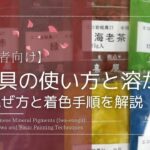
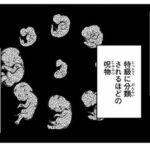


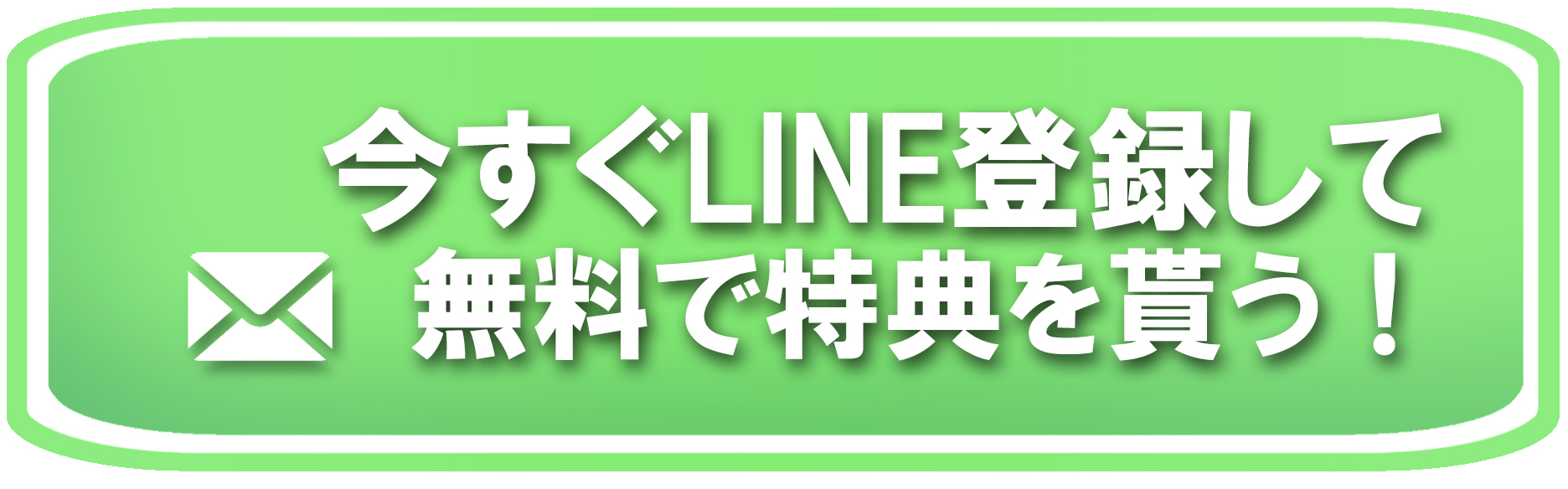

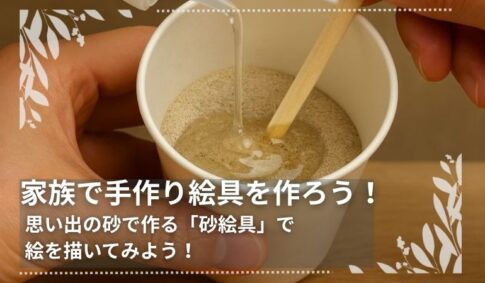

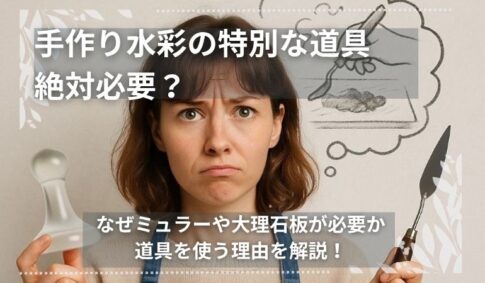

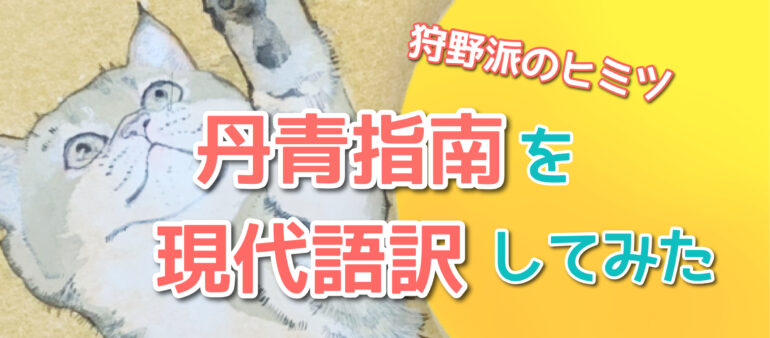

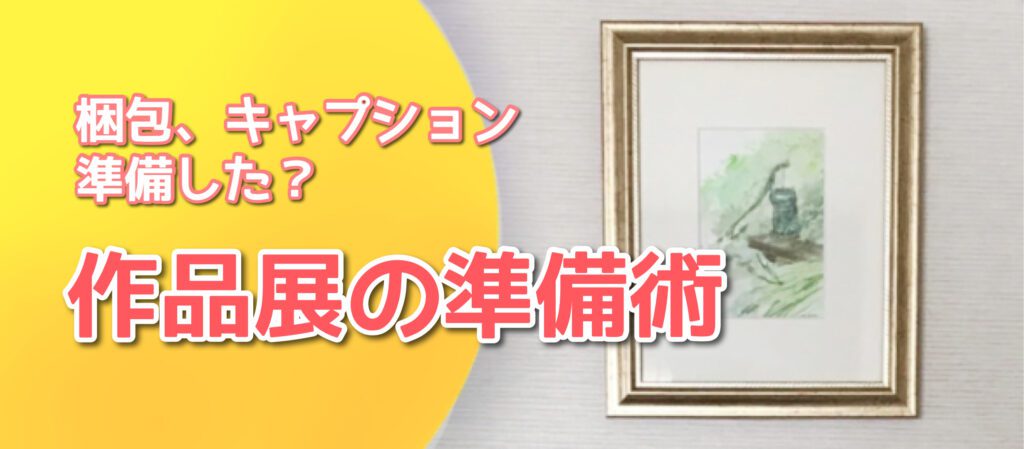
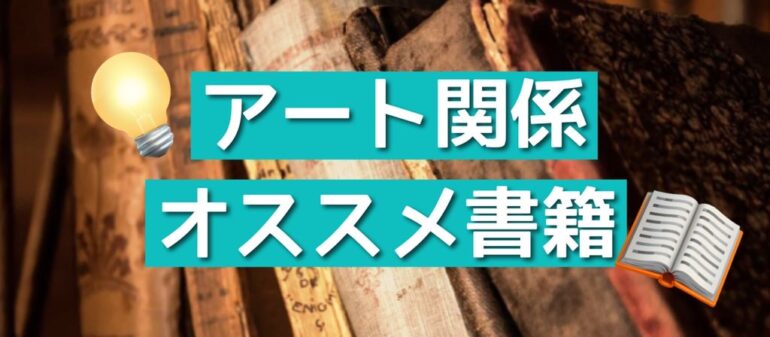
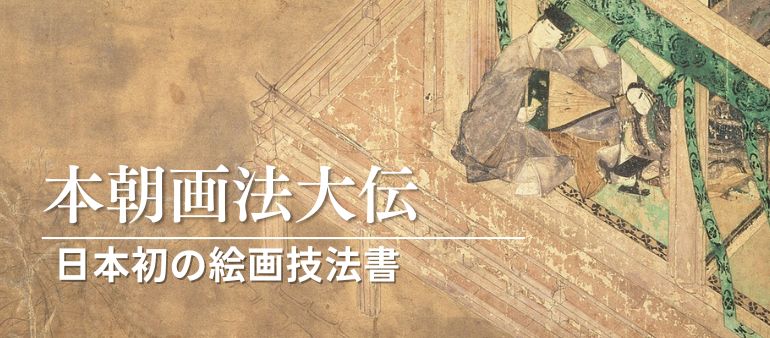

筆の種類を知る前に、まずは構造を理解する必要があります。