こんにちは、日本画家の深町聡美です。
「丹」という色を知っていますか?
もしかしたら
「読めないよ~!」
という方もいるかもしれませんね!
今回は、
- 「丹」とは一体どんな色なのか?
- 日本画絵具の丹の使い方とは?
を狩野派の日本画技法書からも引用して
解説していきます!
結論から言うと、
丹とは黄色みを帯びた赤色、
つまり神社の鳥居に近い色を言います。
日本画絵具の丹は鉛で出来ていて
扱いにコツが要ります!
ではそんな美しい丹色は
どのようなシーンで使われているのでしょうか?
Contents
丹(たん)とはどんな色?

丹は「たん」「に」と読む、
黄色みを帯びた赤色です。
「に」と読む時は「丹塗りの鳥居」
というような使い方をしますよね。
神社の楼閣や鳥居が赤いのも
「丹」色の絵具が使われているからです。
丹の顔料に虫害を防いだり、
錆止めや防腐の効果があるので
神社仏閣のありがたい建物に
使われているんですね!
「鳥居は水銀朱じゃないの?」
そう思ったあなたはとても勉強熱心!
鳥居は水銀朱だけでなく、
丹(酸化鉛)や弁柄(酸化鉄)の
朱色も使われています!
丹塗りは芥川龍之介の『羅生門』にも
登場しています。
広い門の下には、この男のほかに誰もいない。ただ、所々丹塗の剥げた、大きな円柱に、蟋蟀が一匹とまっている。
羅生門/芥川龍之介
丹塗りが剥げていることで
荒廃した京の様子を表しています。

日本画絵具では「丹」は「たん」と読みます。
丹頂鶴(たんちょうづる)の丹ですね。
頭が赤い様子に「丹」という字を使っています。
- 丹とは黄色みを帯びた赤のこと
- 「たん」は丹頂鶴の頭の赤
- 「に」は丹塗りの赤
丹の意味は赤土のこと!

さて、ここで「丹」という言葉の
意味を見てみましょう。
① 硫黄と水銀の化合した赤土。辰砂(しんしゃ)。また、その色。に。
② 鉛に硫黄・硝石を加えて、焼いて製したもの。鉛の酸化物で鉛丹ともいう。黄色を帯びた赤色で、絵の具としまた、薬用とする。和泉国堺で産する長吉丹は上等とされた。
コトバンク

丹って赤土?辰砂?鉛の酸化物?
という感じですよね。
この理由は、
「昔は赤土は何でも丹だった!」
からです。
赤い顔料はいろいろありましたが
昔は厳密に呼び分けられていた訳ではなく
どれも丹と呼ばれていたんです。
- 赤土も辰砂も鉛丹も、区別されずに丹と呼ばれていた!
青丹よしの丹は土を意味し、
青土(青緑青/孔雀石等)を指している。
また、平城京の丹と山の緑の美しさを
指しているともいう。
それではここからは日本画絵具の
丹についてお話します!
丹の絵具は
一体どんな鉱物で出来ているのでしょうか?
日本画絵具の丹の特徴は鉛由来!

日本画絵具の丹は「鉛丹」とも言います。
主成分は四三酸化鉛【Pb3O4】。
金属鉛を400~500度で加熱し、
酸化させています。
ここまで書いたらお気づきと思いますが、
丹は鉛!
そう!毒性ゆえにあまり使われなくなった
鉛白と同じなのです!
ということで食べたり塗ったりはNG!
お子様が使うには不適切な絵具の一つです。
絵具としては水に混ざりにくく
沈殿しやすいという特性を持ちます。
そのため使用時には、後述する
「ちょっとした工夫」が必要です。
絵具の質や保存環境によっては
暗褐色や灰色へ変色する可能性があります。
このように扱いの難しい「丹」を
どうやって使うと良いのでしょうか?
日本画の丹の絵具はどうやって使うの?狩野派の伝統的使い方を解説!
日本画の丹の使い方①よく擦りつぶそう!
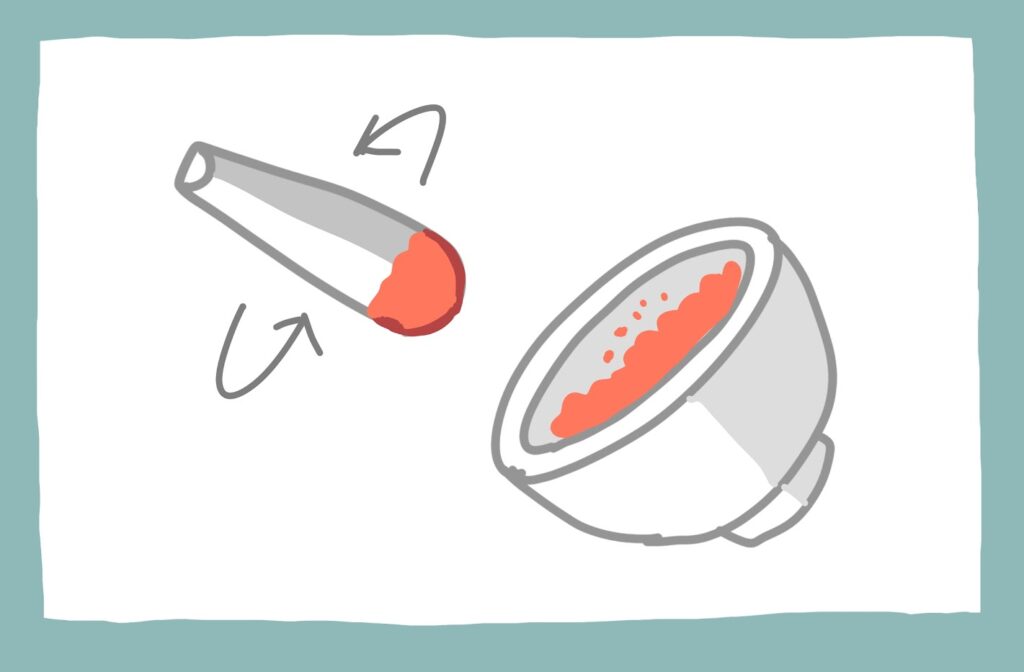
「丹」を日本画絵具として使う時には
以下の手順を踏みましょう。
まずは乳鉢に入れて、乳棒で丁寧に粉状にします。
乳鉢の底に付着するくらい細かくしましょう。
日本画の丹の使い方②膠で溶こう!

乳鉢の丹に、膠を入れて良く練ります。
混ぜにくい時はアルコールを入れてから
膠で溶きます。
丹の粉末全体にしっかり膠が付いたら
水を注いで溶きます。
日本画の丹の使い方③上澄みを絵皿に取り分けよう!
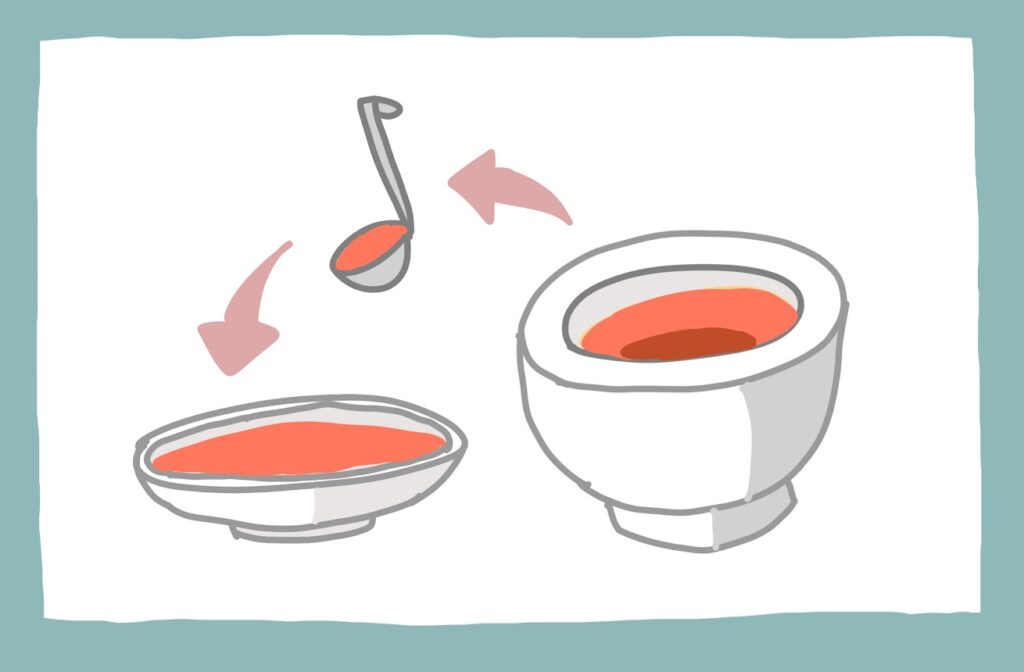
前述したように丹は沈みやすい顔料。
沈んだ顔料はそのままにして、
上澄みだけを絵の具皿に取り分けて使います!
日本画の丹の使い方④皿を炙る!!
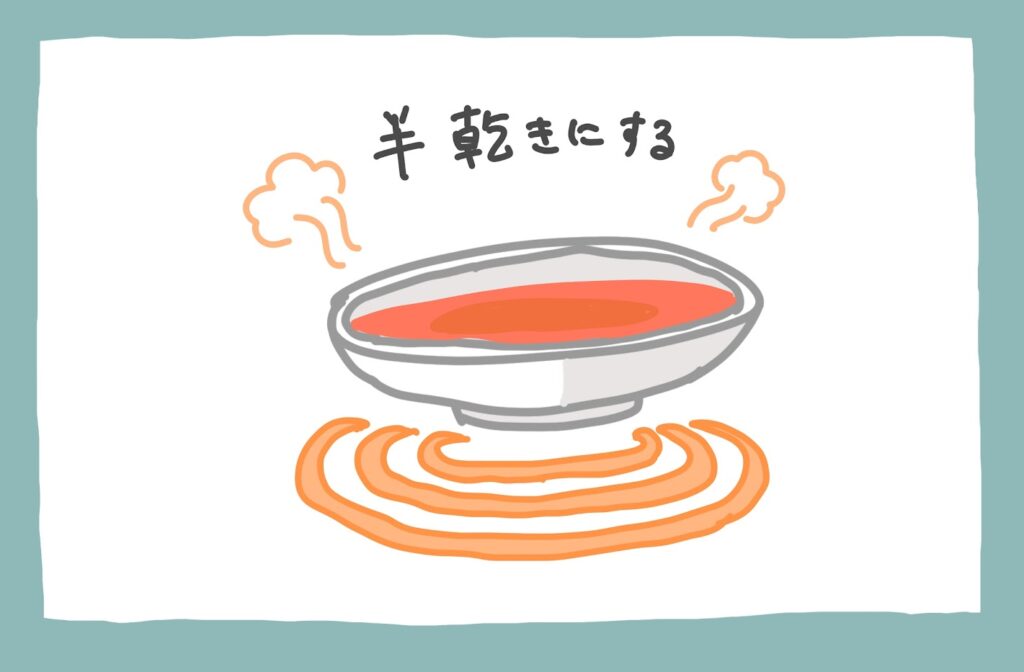
そして丹が入った絵の具皿を
弱火であぶって半乾きにします。
電熱器や保温トレイを活用します。
↑生産が終了してプレミアがついています。
たまにメルカリで見かけますので
その時はチャンス!
水銀が含まれる丹を使う時は
熱さないように!
毒ガスが発生する可能性があります。
日本画の丹の使い方⑤また膠で溶こう!
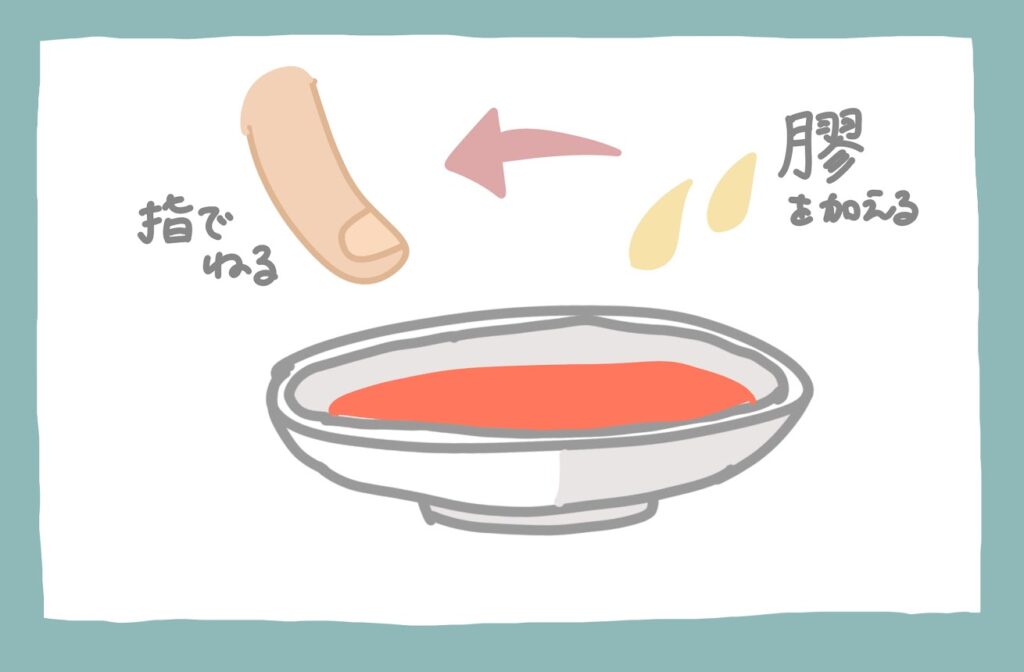
炙って半乾きになった絵の具皿に、
少しの膠を入れ、それを指で練ります。
ほど良く練れたら丹の絵具が完成!
水で溶いて使います。
日本画の丹の注意点

胡粉を混ぜよう!
日本画の攻略本「丹青指南」には
丹を使うときは少しの胡粉を混ぜると良いと
書かれています。
胡粉を少量混ぜることで塗りやすくなり、
発色も良くなるためです。
乾いた丹は使えない!
そして、絵皿の丹は乾いたら
使うことができないと言われています。
絵皿に溶いた後に乾いてしまったら
残念ですがもう一度溶き直しましょう。

・胡粉を加える
・乾いたら溶き直す
この二つを覚えておこう!
まとめー【日本画絵具】丹の使い方
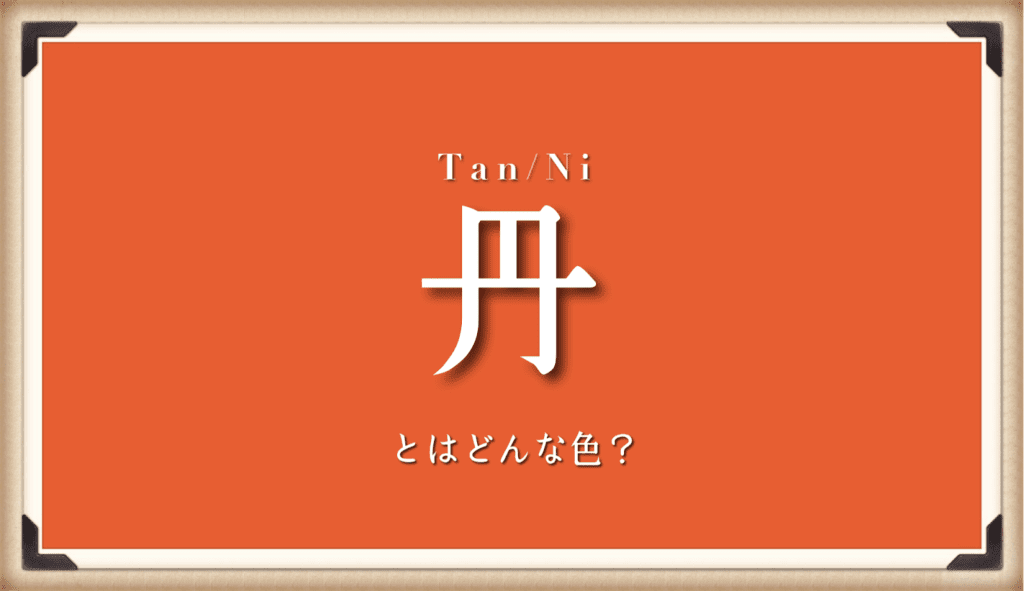
最後までお読み頂きありがとうございます。
丹とは、黄色みのある赤色の絵具でした。
日本画の絵具として使う時には
- 乳鉢で擦り潰す
- 膠で溶く
- 上澄みを絵皿に取り分ける
- 皿を炙る
- 膠で溶く
という手順が必要になります。
手間はかかりますが、
ぜひ日本古来の赤色絵具を使って下さいね!
色と日本画を学ぶにはこれがおススメ!
日本画をするなら必読の書!
日本画の技法が全て分かる!?
独学者には必須の技法書!
専門用語に戸惑うあなたへ
「習ってるんだけど
良く分からない…」
「この粉、なに?」
そんなあなたにおススメの写真付き用語集!
もっと色に詳しくなろう!
色の種類や色名の理由が
ちゃんとわかる!
学術的に色を学びたい方におすすめ!
色で心を操ろう!
色の力は未知数!
自分を変るのはもちろん
他人だって操れちゃう!?
世界で一番人気な色って!?
『丹青指南』は、江戸時代の絵師たちが使っていた技法書です。
色の名前や使い方が細かく書かれた、
貴重な日本画の資料を
現代語訳+注釈つきでまとめました。
👇本格的に学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください👇
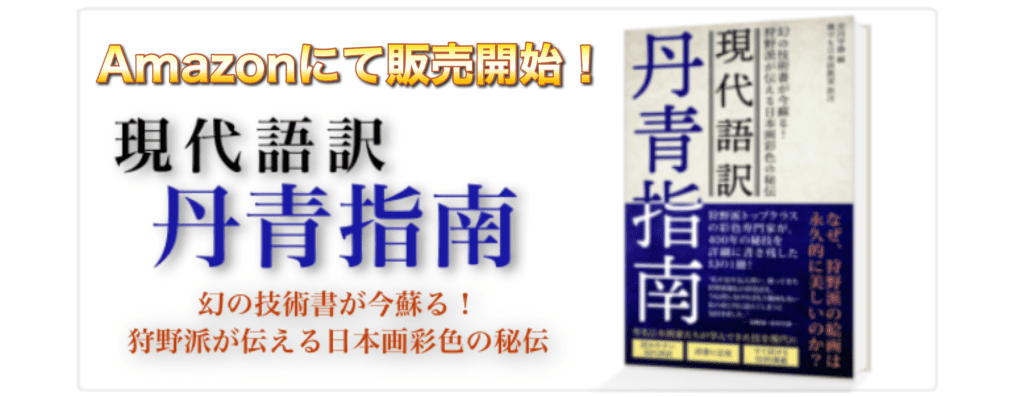
色のことをもっと知りたいときは?
⇒【危険】絵の具には毒性があるって本当!?【子供が食べても大丈夫?】
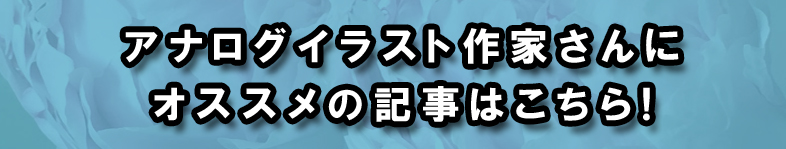

前の記事はこちら!
⇒【100均】ウォーターパレットの作り方!アクリル絵具を乾かさず使う!【ガッシュ】
次の記事はこちら!
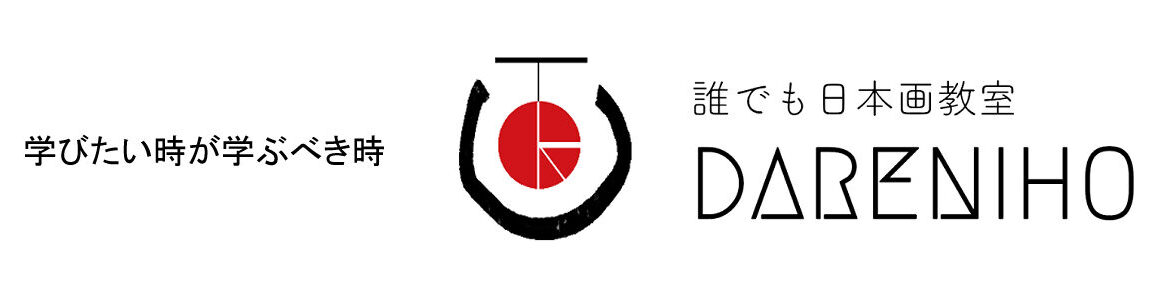



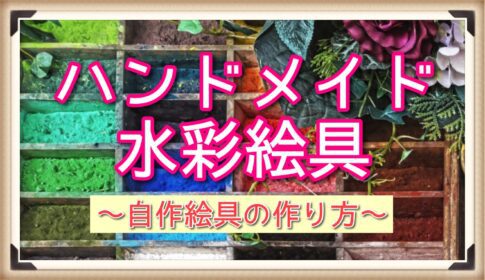

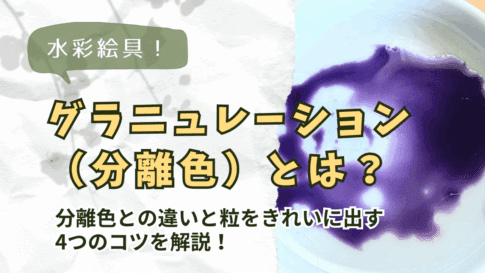

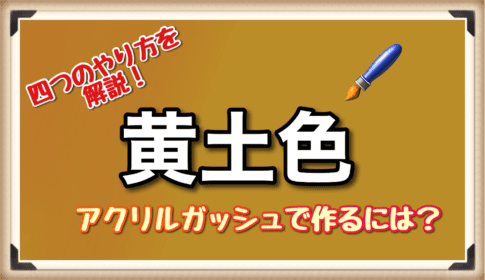

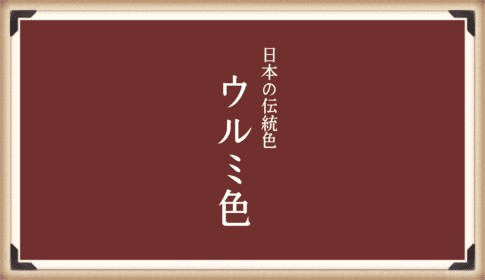
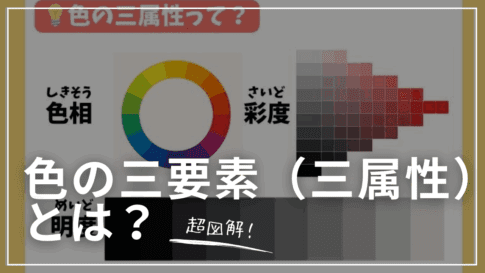
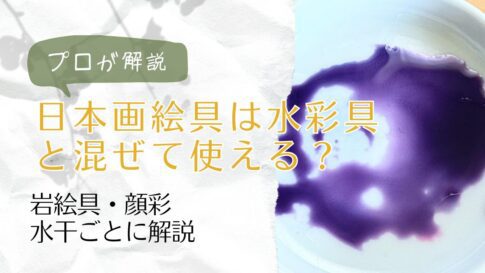

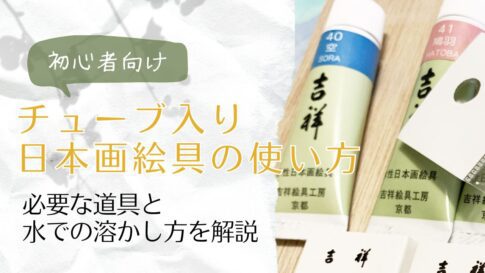
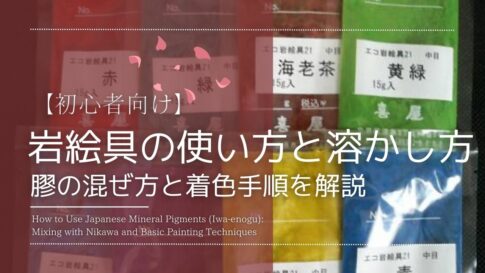

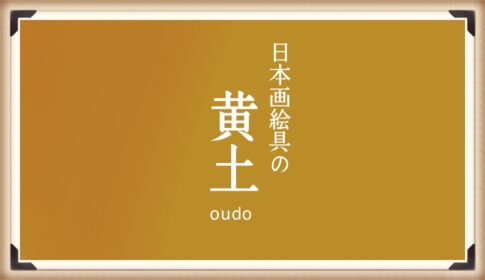
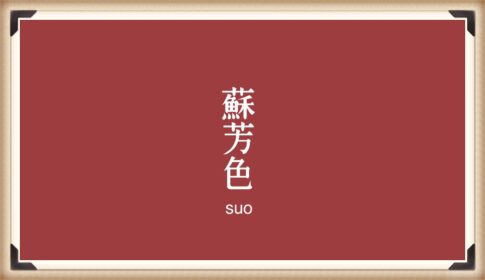
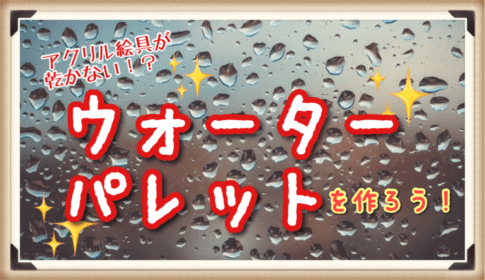
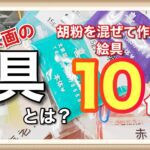
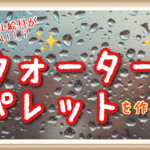


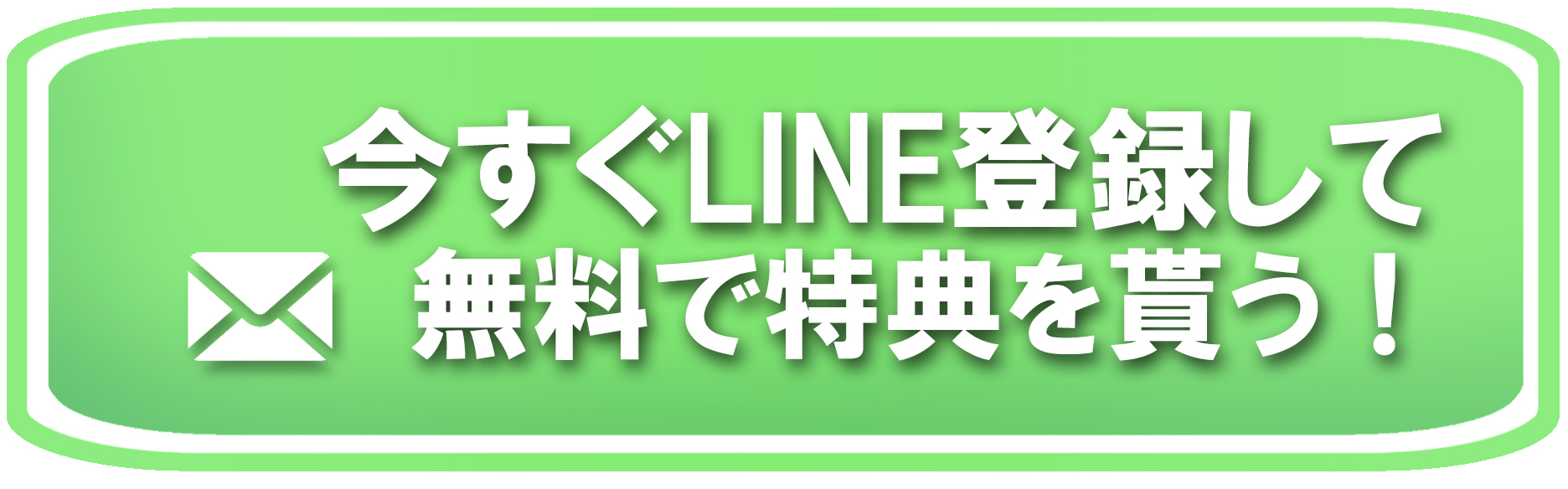

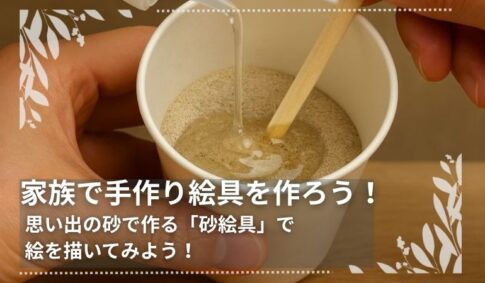

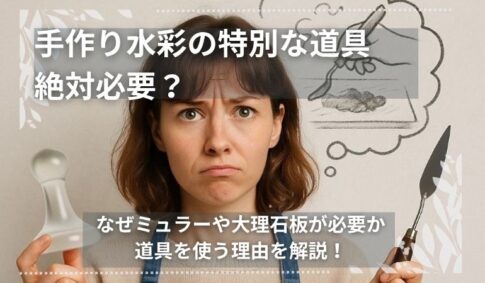

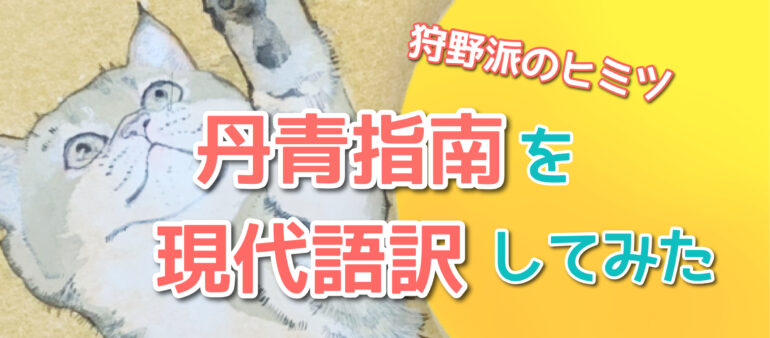

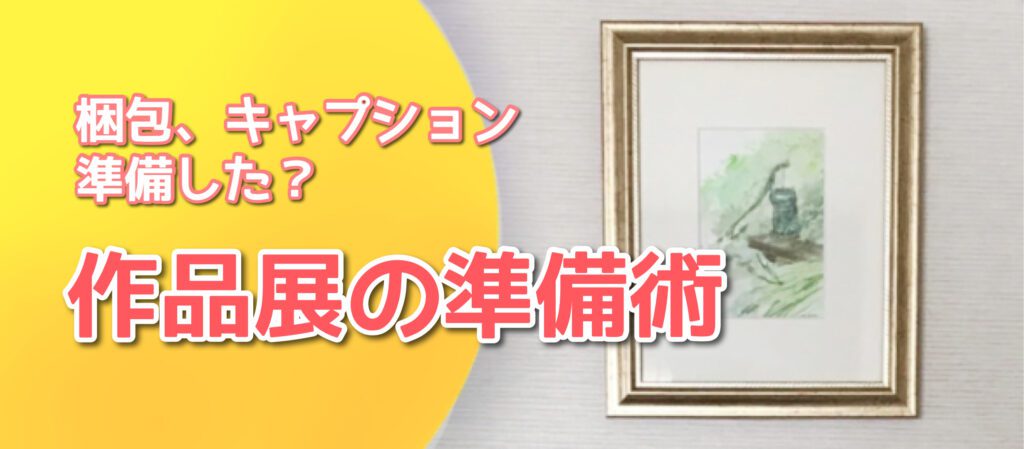
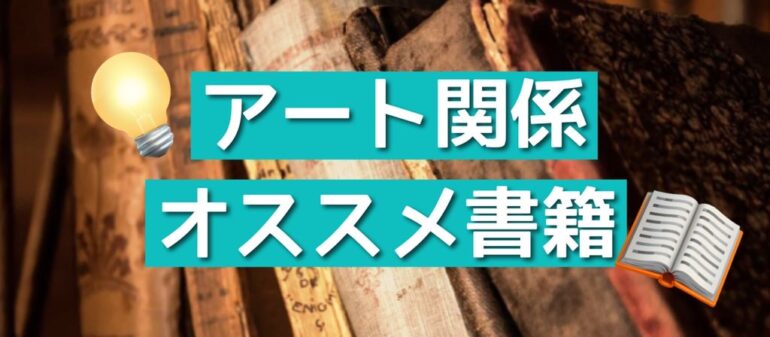
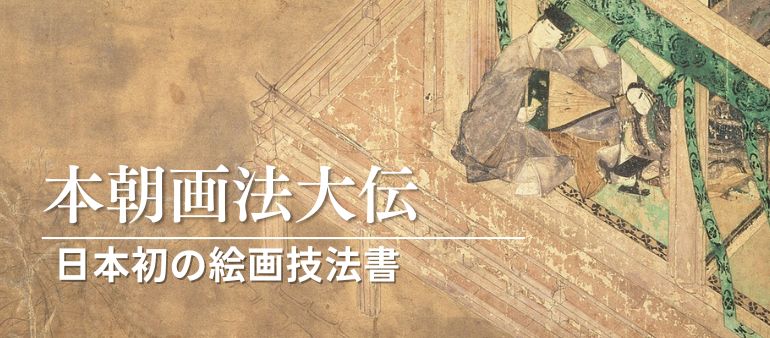

丹は「たん」とも「に」とも読むんだね!